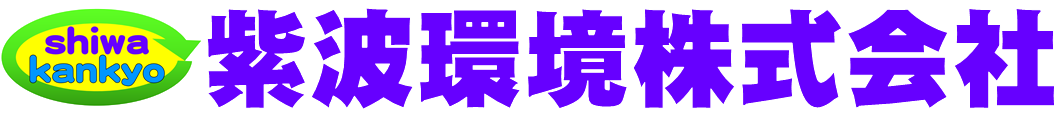水への影響 有機汚濁・富栄養化・有害物質
静かに始まり、川の流れは私たちの暮らしを映す鏡のようにある。
その澄んだ水面には、日々の生活や産業の営みの痕跡が、ひとつ、またひとつと落ちていく。
見えない汚れが積もるとき、水は言葉を失い、命の循環も静かに歪む。
そこにあるのは、単なる「汚い水」ではなく、生活環境の保全や公衆衛生の向上に深く関わる問題である。
しかし、その流れは濁ることもある。
有機汚濁は、生活排水などに含まれる有機物が、好気性微生物によって分解される過程で酸素を消費し、水中の溶存酸素(DO)を低下させる現象をいう。
汚濁が著しく進むと河川は嫌気状態に陥り、魚介類や水生昆虫などの生息環境が悪化する。
富栄養化は、窒素やリンといった栄養塩が過剰に流入し、藻類(湖沼や海の植物プランクトン)が異常繁殖することで起こる。
これにより、水の透明度が失われ、海域では赤潮や青潮(苦潮)が発生し、水産被害を引き起こすこともある。
有害物質による汚染は、鉱業や工業の排水に含まれる特定の有害物質が原因となり、かつての水俣病(アルキル水銀)やイタイイタイ病(カドミウム)といった公害病を生じさせた。
水質汚濁とは、自然の「均衡」が崩れた状態であり、目に見える汚れ以上に、社会全体の呼吸の乱れを映す現象といえる。
だからこそ、整える仕組みが要る。
浄化槽は、都市郊外や地方部において、し尿や生活雑排水を適正に処理するための恒久的な生活排水処理施設として重要な役割を担っている。
その構造は建築基準法によって、維持管理は浄化槽法によって規制されている。
浄化槽の放流水は、生物化学的酸素要求量(BOD)1リットルあたり20mg以下など、環境大臣が定める水質基準を満たす必要がある。
また、浄化槽管理者には、年1回以上(環境省令で定める回数)保守点検および清掃の実施義務が課せられている。
保守点検は浄化槽管理士が、清掃は浄化槽清掃業者がそれぞれ担当し、両者の連携と技術の向上が求められる。
水を守ることは、地域を守ること、人を守ることと重なっていく。
整うことで、磨かれる。
私たちが見落としがちな日常のひと滴を大切にすることが、純化のはじまりになる。
浄化槽を使う者は、殺虫剤や油脂、強酸・強アルカリ性洗剤など、機能に支障を及ぼす物質を流さないように心がけなければならない。
どれほど高性能な浄化槽であっても、維持管理が不十分であれば本来の浄化機能を発揮できない。
誠実さとは、目に見えない場所で責任を果たすこと。
その積み重ねが、生活環境の保全と公衆衛生の向上につながっていく。
静かな手が未来を変えていく。
水を濁らせるのも、人。澄ませるのも、人。
浄化槽の整備促進と適正な維持管理の徹底という小さな選択の一つひとつが、やがて地域の景色を変えていくのだろう。