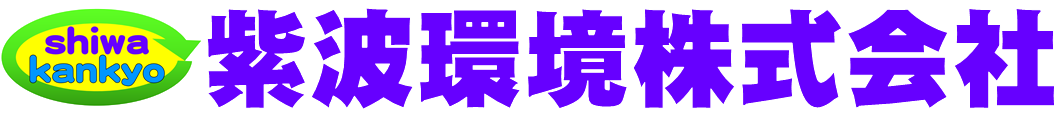汚泥が蓄積すると処理機能が失われ“水が死ぬ”
空気が静かに動き出す朝、澄んだ水の流れに目を凝らすと、そこには人の営みの痕がそっと溶け込んでいます。
水は、私たちの暮らしの中で息をしている
存在です。しかし、その呼吸を支える「浄化槽」の仕組みは、
公共用水域等の水質の保全と、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的として、その設置、保守点検、清掃及び製造について規制が定められています。
その均衡は微かに揺らぎます。
浄化槽の底に沈む「汚泥」や「スカム」が長期間かけて溜まっていくと、本来の処理機能が徐々に失われていきます。
有機汚濁物質は、主に好気性微生物によって酸化分解されますが、汚泥の蓄積により水中に溶解している溶存酸素濃度が低下し、微生物による消費速度が酸素の溶解速度を上回ると、水生生物が生息できない「嫌気状態」に至るおそれがあります。
これは、清掃を怠った槽内では、分解しきれない有機物が腐敗し、最終的には公共用水域の汚染源となることに繋がります。
だからこそ、共に整える時が来ました。
浄化槽の「清掃」とは、浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引き出し、その引き出し後の槽内の汚泥等の調整、並びにこれらに伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行う作業を指します。浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合を除く)、この清掃を実施する義務があります。
バキュームカー等を用いて汚泥を適切に抜き取る清掃の現場は、単に“汚れを取る”仕事ではありません。清掃は環境省令で定める技術上の基準に従って行わなければならず、浄化槽清掃業者は、保守点検業者と連携を十分にとり、汚泥の収集、運搬、処理処分を含めた適正な維持管理を確保することが重要です。清掃業者には、地域の水循環を守るための専門的な知識と技能が求められます。
この「清掃」という営みの根には、「誠実に水と向き合う」姿勢があり、その技術と手仕事が地域の安心を支えています。汚泥を取り除くという行為は、生活環境の保全を確実にするため、水を生かし、未来の世代へと清らかさをつなぐ不可欠な責務なのです。